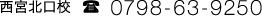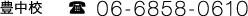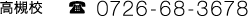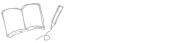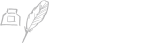2026.01.31Vol.83 自信と謙虚のあいだ
小学生の頃からドキュメンタリー番組が好きだ。これまで見てきたものの中で印象に残っている一本を問われたら、≪情熱大陸≫の世界的なヴァイオリニストの庄司紗矢香に密着した回を挙げる。調べたところ19年前の放送だった。時の流れはおそろしい。それでも記憶がある程度の新鮮さを保っているのは、庄司氏があまりにも気風の良い女性だったからだ。彼女はパガニーニ国際コンクールで史上最年少の16歳で優勝したことで、スター演奏家の仲間入りを果たした。しかもこのコンクールは「1位該当者無し」が珍しくないくらい審査基準が厳しい。そして、番組内ではおそらく表彰後に行われた記者会見の様子が一部流されたのだが、記者から感想を尋ねられた庄司氏は涼しい顔で「優勝すると思っていたけれど(実際に1位を獲れたのは)やっぱり嬉しいです」と返していた。なんてクールな発言だろうか!放送当時9歳だった私は、彼女のように堂々と自信を持っている日本人を目にしたことが無かった。優秀な子や才能のある子じたいは身近にもいたし、彼、彼女たちの性格もそれぞれであったが、自身が力を入れている分野の話を学校の教室で持ち出すようなことはしなかった。また、一芸に秀でていようがいまいが「自分なんて大したことない」という謙遜のポーズを取ることが良識なのだと、大人たちからは教えられてきたし、子どもたちの方も集団生活を送る上で重要な処世術だと肌で理解していた者が大半だったはずだ。空気を読むのが下手な私でも、出る杭になっては生きづらいだろうとは感じていた。そういう常識の下で生きていたのもあり、10代ですでに一流の精神が確立されていた庄司氏の姿は衝撃的だった。プロフェッショナルとは、自分の立ち位置を正確に把握しながら、ゴールの無い研鑽の道を歩むことができる人物なのだと教えられた。また、努力を続けられているのは、目標を達成した喜びを純粋に受け止める素直さもあるゆえだ。数値化が難しい音楽の領域において己を客観視できる鋭い感性は生まれ持った素質によるのだろうが、トップランナーに対して「天才はやっぱり違うなぁ」という漠然とした尊敬を抱くだけで終わるのは勿体ない。彼ら、彼女らの活動に触れることの意味は、凡人なりに「より良く在る」ための視点を与えてくれることにある。
庄司氏の発言が最近になって脳裏に浮かんだきっかけは、国語講師に応募してきた方の面接を通して、相手は「作文が得意です」と(たとえ表面上でも)断言するまでに葛藤はあるのだろうか、という疑問が湧いてきたことだ。私の知る限り、著名な職業作家は作品に誇りは持っていても、だからといって「執筆が上手いです」とはアピールしない。誰よりも言語化能力と構成力に長けているのに。だが、言葉を大事にする彼、彼女らが「自分なんて大したことないんです」などと表面的な謙遜をするはずは無いだろう。
肩を並べるようであまりに恐縮なのだが、私自身が「得意」という自己認識を持っていない、より正確には「持ってはいけない」と肝に銘じている。これまでの「志同く」でも今となってはぞっとする内容のものを掲載してしまったのは一度では無い。逆に、他の講師から有難いことに高評価を貰えた場合でも、実態は「全然きれいにまとめられなかった」と半ば絶望しながらのブログ更新だったりする。要は、当の書き手にとっても文章の質は発表してから決まる部分があるからこそ悩む。掴み所の無い相手との格闘のようなものだ。ちなみに、あの村上春樹氏は空想上の「うなぎ(の蒲焼)」と協力しながら闘っているらしい。彼いわく、小説とは、筆者と読者とうなぎが「三者協議」を行わないとが生まれないものだという。私は内田樹氏の著作『先生はえらい』での引用文を通して村上氏の創作の裏側を覗いたのだが、第三者的な視点をうなぎのキャラクターに設定している理由は明かされていなかった。内田氏は「それを嫌う日本人はほとんどいないけれど、(産卵場所のように)謎に包まれた部分も多い」点が比喩表現として秀逸だと評価しているため、一般論を想定して物語を練るという意味なのだろう。つまり、「伝えたい」という衝動に任せてただ好きなように書き連ねていては、かえって伝わらない文章が出来上がってしまう。そして、「志同く」の場合に引き寄せて考えると、テーマに自由度に甘えることなく、日常生活で琴線に触れた事柄について「ここから生徒と親御様が何か気づきを得られる内容になっているか」を見直すことと繋がっているのではないか。
面接の話題に戻る。応募者は国語の専門塾と自分をマッチングさせるべく「得意です」とあえて言い切っている面もあるだろう。ただ、もう少し踏み込んで、国語に対してポジティブな気持ちを抱くようになったきっかけを教えてもらうと、「何気なく書いた作文を大人に褒めてもらえたから」や「入試科目の中で一番点数が良かったから」という答えが返ってくる。それらはご本人の自信に繋がる大事な経験だろう。ただ、個人的には、苦しみの過程を経て「作文を好きになった」もしくは「今でも得意ではないけれど重要性を認識するようになった」という結論に至っている人の方に魅力を感じる。言葉を紡ぎ出すことの困難さに正面からぶつかってきたがゆえの謙虚さが滲み出ているからだ。
2026.01.23社員のビジネス書紹介㉘
三浦のおすすめビジネス書
鈴木義幸 『新 コーチングが人を活かす』 ディスカヴァー・トゥエンティワン
まず印象的だったのは、自分自身へのコーチングともいえるマインドセットについても都度触れていることだ。コーチングとは用意した答えに相手を導くのではなく、「相手なら何かを見つけ出せる」と信じて問いを投げかけ、一緒にその答えを深めていくものだとしている。その「問い」は、自分自身に投げかけてもいい。例えば対人関係で悩んでいるのであれば、その気になっている相手に対する質問をいろいろと考え、その人になったつもりで答えてみる。これによって相手の立場に立つことができる、というものだ。目標設定に関しても、漠然としたところから質問を重ねることで少しずつ具体化していき、最終的にはそれをもう一度抽象化するという流れを、一人で行うこともできるのだ。もちろん、誰かと対話しながら行う方が理想的ではあるだろうし、それがコーチングなのだろうけれど。
また、生徒とのやり取りにも通じるところがあった。どうしても答えやこちらの考えを先に言ってしまいたくなるものでもあるが、そうではなく、まずは相手の力を信じて、切り口を変えながら問いかけを続けて行くことが大切だ。とはいえ、それは相手に丸投げすることではない。指導の際には、自分なりにある程度の見解を持っておきながら、相手が自分の力で何かに辿り着くのを最優先させる。自分の思う何かがたったひとつの答えではない、その当たり前のことを肝に銘じておきたい。
最後にもう一つ。どうしても行動を習慣化できないと悩んでいたのだが、本書でそれは「行動の過程を考え、その苦労を想像していやな気持ちになっているのが原因」、「過程ではなく結果を思い浮かべるといい」と述べられていた。まさかコーチングの本で出会うとは思わず、だからこそ印象深かった。
竹内のおすすめビジネス書
杜師康佑 『超凡人の私がイノベーションを起こすには』 日本経済新聞出版
これが「タイトル買い」というものなのだろうか。
革新とは一握りの天才によるひらめきで起こると考えられがちである。いや、アイデアが出てこない自分に対して、そういうものだと思いたくなってしまうというのが正しいかもれない。しかし日経新聞で長くビジネス関連の記事を書き続けてきた著者にとっては、社会を変えていく新しい製品やサービスは、降って湧いてきた発想によってではなく、挑戦と失敗を繰り返して誕生するものなのである。本書では、これまで取材した数々の企業の実践例を取り上げるのはもちろんのこと、仕事と並行して慶應の大学院でシステムデザイン・マネジメントを学んだことを活かして、その裏側にある理論を分析している。実例に触れて「そんなの浮かばないわ」に留まるのではなく、どのような見方、考え方がヒントを引き寄せるのか、反対に、自分や組織の抱えている課題が何かを探っていく指針になる。
本当に多くの例が登場しているが、RIZAPが展開している「chocoZAP」について取り上げた章で述べられている「まずはやってみる」という考え方は、行動になかなか移せない自分が改めて取り入れなければならないことである。「コンビニジム」という、他のフィットネスジムにはない面が売りである。フィットネス以外に何が求められているかというのを模索し、社員たちの提案したものをまず置いてみる。残らなかったものの方が多いのだろうが、セルフネイルや脱毛ができるというのは「とにかく出してみる」という段階を踏んでいることによる。PDCAサイクルのC(check)を充実させるために利用者アンケートも積極的に行っており、そのためにPlanとDoをできる限りスピーディーに進めるというのが徹底されている。何となくではなく目的を持ってサイクルを回すことがやはりアイデアを生み出すきっかけにもなりえるのだ。
徳野のおすすめビジネス書
辻太一朗/曽和利光/細谷修平/矢矧春菜 『採用一新 さらば!ガクチカ頼み』 株式会社日経BP
講師の採用面接の時間が迫るといつも憂鬱な気分になる。他者の人格をテストするような行為じたいに(今でも)気が引けるし、30分近く色々と話し込んだ相手を場合によっては落とさないといけないからだ。加えて、そもそも「良い人材」を見極める基準や方法が自分の中で明確になっていないのも不安の種だ。他の社員による面接に同席した機会は何度かあるものの、それの「見よう見まね」のような状態でここまで来てしまった。一教室の責任者としてそれでは流石にまずいと感じて手に取ったのが今回の一冊である。
4人いる著者たちは皆、リクルート社の「学ポタ」推進委員会のメンバーである。この「学ポタ」、正式名称は「学業場面に表れるポータブルスキル」は、新卒の就活でよく取り沙汰される「ガクチカ」、つまり「学生生活で力を注いだこと」に対置される概念だ。日本の大学生は欧米や中国の若者と比べると入学後の勉強量が少なく、国際競争力で引けを取る一因になっているという言説を耳にするが、それは企業による採用のあり方が生んだ構造的な問題である。インターネット経由の応募が一般的になって以降、膨大な情報処理を求められるようになった企業は、エントリーシートと性格適性テストを用いて効率性を追求し始めた。その影響で、大学での専門研究よりも親近感の湧くサークル活動やボランティア、アルバイトでの経験が注目を受けやすくなった。また、就活生側も短い時間で採用担当者に強い印象を与えることを目指して「伝え方」を洗練させる方に重きを置くようになり、エピソードの脚色も横行し出した。すると、演出力のある応募者に有利な状況が作り出されることになるが、その現状は学生たちの内に「自分の事を正直に語っても選考に通らない」という先入観を植え付けているだけでなく、人材のミスマッチを防ぎたい採用担当者は相手が語る内容の真偽を見極めることに注力するようになった。互いに心理的負担が大きいのだ。
そして、「学ポタ」は就活に関わる不信感を軽減するために考案されたシステムである。採用の確実性を高めるための着目するべきポイントは「定量的な成果」と「思考の一貫性」であり、それを測る上で学業の成績は最適な素材となる。さらに、GPAなどの数値化された「結果」だけではなく履修科目の内容や単位の取得難易度も可視化することで、学生の知的好奇心の方向性や目標に対する計画性を浮き彫りにしやすくなる。それらは仕事の現場で生きる素質だ。さらに、企業側が信頼に足るデータを求めることは若者たちへの「メッセージ」にもなるので、学生たちの間に「まずは腰を据えて勉強するべきだ」という価値観を浸透させる効果も期待できる。
個人的な話に戻るが、本作を読み始めてから学生講師との面接が2件あった。緊張は相変わらず襲ってきたものの、受験に関して「なぜ、今通っている大学と学部に決めたのか」、第1志望校と縁が無かった場合は「自身の受験をどう振り返っているか」を教えてもらうことの狙いをきちんと把握した上で臨めたのは一つの収穫だ。あとは、19歳の若者たちの具体的な夢についてあれこれ掘り下げるのは純粋に楽しかった。
2026.01.16Vol.82 淡々と、単々と(三浦)
1/16、受験前日である。毎年、この時期に志同くを書いている気がする。そしてそのたび、受験にしっかり絡めないとと思いつつ、大した受験経験のない自分には偉そうなことも言えないしと悩み、結局はいつも通りに書くことにしている気もしている。私が何か書くからといって、誰かの結果が変わるわけではない。ただやり切ってくれればそれでいいし、そのことはもう、皆わかっているはずだ。
なので、今回は以前に少し書いていた文章を再利用させてもらうことにする。
Amazonの電子書籍サービスことkindleには専用端末がある。10年近く前に思いつきで買い、それから数年使ってからはしばらく部屋の片隅に眠っていたのだが、先日偶然発掘し、再会を果たした。記憶になかったので調べてみたところ、2013年の第6世代というものになるらしい。最新のものは2024年発売の第12世代らしいので、かなり古い型で間違いないだろう。
最新型を触ってみたことはないが、性能としてはそれよりも格段に落ちているのはよくわかる。ページ送りに若干のラグが発生するし、本を選んで開くまでのラグも長い。久しぶりに触ってみた感触としては値段(いくらか忘れたが、8000円くらいの感覚だった覚えがある)の割には使いづらいかも、といったところだったのだが、それだけで一冊を読み切ってみると、思っていた以上に読みやすかったことに気がついた。ページ送りのラグはそのまま紙の本をめくる時に似ていたし、一度本を開いてしまえば、閉じるまでは立ち上がりの遅さも気にならないからだ。
もともと、電子書籍はそれほど好きなタイプではない。紙の本のほうが目に入る頻度が高く、読まずに終わることが少ないから。あるいは、電子書籍は目が疲れるから。さまざまな理由から「やっぱり紙だな」と思いつつ、とはいえ部屋に置ける数には限りがあるし(積んでいる数も大変なことになっている)、電子書籍のセールを見かけるとついそちらを手に取ってしまうこともある。だから「電子書籍ってこんなに読みやすかったっけ」と感動して、ずっとkindleの端末を持ち歩いている。
本を読むためだけのデバイス、と思うと、なんだか面白い。そもそもスマホやタブレットなど、既に持っているデバイスで読むことが電子書籍の目的だと思い込んでいたからだろうか、「本を読むために電子機器を買う」というところに妙な面白さを感じる。電子書籍のメリットは様々ある。紙の本と違って場所を取らないこと、そして持ち運びが容易なこと、購入さえしていれば出先でどの本を読むか選べること、そういったものが挙げられるだろう。それでいえば、電子書籍の良さを生かしながら、より良い読書体験に繋げているといえるのかもしれない。
意見作文の一環として取り組む、佐藤雅彦氏の『毎月新聞』を基にした教材に、「単機能すぎず、多機能すぎないものを考える」というテーマがあった。つい最近悩んでいた生徒がいたこともあって頭の片隅にあったのだが、上記のkindle専用端末なんてものは、まさしく単機能なものだろう。色々な用途に使えるタブレットとはまったく違い、電子書籍、しかもkindle専用のデバイスなのだから。でも、だからこその良さがある。他のタブレットとは違って、読書に最適なライトが用いられており、目が疲れない。このライトで動画を見ることはできないが、文章を読むには、普通の本よりも場所の明るさを選ばないという点では優れているとすらいえる。
時代は便利になっていく。あらゆることはスマホやパソコンで解決し、大は小を兼ねるがごとく、さまざまに多機能なものが生み出されていく。ただ機能的であるだけでは足りず、他の付加価値を与えることが、一番手っ取り早いからだ。けれど、どこまでもひとつのことを突き詰めた「単機能」も、それはそれで大切なのだろうと思う。人間は単機能ではありえないが、ひとつのことだけに集中する、そういう時があってもいいのかもしれない。
ちなみに、前回少し書いた風呂上がりのストレッチは、結局「ストレッチをする」というのが頭から飛んでいる日が多かったせいで全然果たせなかった。ただ、その数少ない成功例から、「余計なことを考えないように、風呂上がりから数字を数えてすぐに行う」というほうが効果があることがわかった。考えすぎて眠れないときに、ただ脳内で数字を数えるのと一緒だ。うん、やっぱり脳も時には、単機能なほうがいいこともある。
2026.01.09Vol.81 見えるものの向こう側にあるもの(豊中校・湯下)
NHKの朝ドラ「ばけばけ」が、なかなか面白い。主人公トキは最初の夫とも生涯の伴侶とも怪談が共通の趣味で、その舞台となった現地でデートして、大いに盛り上がったりする。そういう場所が生活圏の中に現存していたということがまず驚きだが、明治の時代にはまだまだそんな妖が生活の中で息づいていたのだろう。現代の若い世代にとっては明治も江戸も大差ない大昔だろうが、明治生まれの祖母と大人になるまで同居した私には、そういった、薄皮一枚で妙なものが隣り合う感覚は馴染みがある。
例えば、私が高校の頃に飼っていた猫、ゴンの話。当時、猫は放し飼いが一般的で、雄は五六歳にもなると家出するというのが相場だった。ゴンもご多分に洩れず旅に出て、最初は三日置き、それが一週間、一ヶ月と帰ってくる間隔が間遠になったある日、学校から帰宅した私に祖母が「ゴンが今日顔を見せに来たよ。でもあの子はもう帰ってこないよ」と告げた。なんで、と聞き返すと「家の四隅に座ってきちんと挨拶して行ったから」とのこと。私としては「へー」としか答えようがなかったが、果たしてゴンはそれきり姿を見せなかった。その不可解に気づいたのは、ずっと後になってからだ。確か、杉浦日向子さんの「百物語」という漫画を読んだのがキッカケだった。怖いというより不可思議な話を集めた中に、「ある小僧がお使いの帰り、ふと覗いた垣根の奥に、日向の縁台で白魚をより分けている老婆がいた。その背後にいた煤けた猫が、『ばばさん、それを俺に食わしや』と呼びかけるのへ、老婆は手も止めず『おぬしは何を言うぞ、まだ旦那どんも食わしやらぬに』とたしなめた」という話があったのだ。この話で興味深いのは、その小僧が猫が喋るのを聞いてもびっくり仰天したりしないところだ。慌てず騒がず、もう一言何か言わないかと待ち続けるのだ。それを読んだとき、私はふと祖母とゴンのことを思い出した。すっかり忘れていたが、あのときゴンは本当に、そんな挨拶をしたのだろうか?いやいや、祖母がそれに一々付き合ったはずがない。仮に本当だったとしても、なぜ祖母はそれが猫なりの別離の儀礼だと知り得たのだろう?
祖母は既に他界しているので、本当のことはわからない。ただ、「ばけばけ」の世界がそうであるように、祖母もまた昔の、田舎の人だったから、人知の及ばぬものがあるということを素朴に受け容れ、八百万の神々として日々の生活に溶け込ませ畏れ敬ううちに、それらの声なき声を感知する術を自然と身に着けていたのかもしれない。それは多分、高度な科学技術に頼る生活に慣れた我々現代人が喪った感覚なのだろう。
「?」を解き明かそうとするとき、人はそれぞれの特性と言うか、「らしさ」を発現するのではないだろうか。例えばメアリー・ノートンがちゃんとしまっておいたはずの針や安全ピンがなくなってしまう奇妙さから『床下のこびとたち』(ジブリ映画『アリエッティ』原作)を紡ぎ出したように、あるいはリンゴが落ちるのを見てニュートンが万有引力の法則を見出したように。そして祖母が、可愛がっていた猫の何気ない仕種や目つきから、そのメッセージを敏感に察知したように。
そう言えば以前、こんなことがあった。息子が中学生の頃、塾か何かで帰宅が遅くなったので、犬の散歩がてら迎えに行ったときのことだ。家の近くで、向こうから歩いて来る息子を見つけた。ほぼ同時に息子も気づいたようだったが、何故か立ち止まり、こちらを透かすように窺い見ている。そこは車が通れない川沿いの細い路地で、反対側は竹藪、川の向こうは雑木が鬱蒼と生い茂る山で夜半には猪が出る獣道が通っている。人通りも途絶え街灯もまばらな朧の闇の中、さては異形の者と見間違えたかとおかしくなり、犬を放してやると勇んで駆け寄ったのに安心したのか彼は嬉しそうに屈んで出迎え、リードを取るとじゃれつく犬ともつれるように歩み寄ってきた。さっきはどうしたのと尋ねると、彼はちょっと口ごもったが「幻かと思ったんだ」と答えた。
「幻?」
「うん。幸せな幻」
実際は、やっぱり亡霊か何かと怯んだのかもしれない。しかし私はそれを信じた。ばかりか、親馬鹿で恐縮だが「ああ、この子は身も心も健やかに成長しているな」と安堵に似た喜びさえ感じたものだ。もともと彼は幼少期「バムとケロ」シリーズの絵本が大のお気に入りで、小中高とアイドルは一貫して「ムーミン」という、人間とは異なるものたちの静かで安寧な世界を愛する子どもだったから、その受け答えはいかにも彼らしかったのだ。
こういったことは、生徒の作文を読んでいて日々感じるところでもある。例えば以前、『きまぐれロボット』に取り組んでいた子どものものが面白かった。この教材では、解釈の仕方に一応スタンダードがある。そのときの話の内容としては「S博士新発明の食虫植物を分けてもらって喜んだR氏だったが、それは捕食する害虫がなくなると枯れてしまうため、冬場は手間暇をかけてボウフラを育てねばならず、これでは便利なのかどうかR氏はわからなくなった」というもので、通常はこの最後の部分に着目させて害虫を捕る花のために虫を育てる矛盾に気づかせ、目的を見誤ってはならないというところに導くのだが、その子は「価値あるものに代償を払うのは当然で、蚊に悩まされるくらいならそれぐらい辛抱するのが当然だ」というのが言い分だった。一理あるのでその線で進めていくと、「価値観は人それぞれなので、自分に合うかどうかを先に調べるべき」と斬新な展開となった。この子はいつもちょっと頑固なくらいにマイペース、我が道を行くタイプだっただけに、いかにもな着地点だった。これは彼に限ったことではないが、面白い着眼点やユニークな発想で生徒から驚かされることは多々ある。その都度、正しさや己の尺度に拘って柔軟さを欠いた自分に気づかされる。また他の生徒で、入塾したてでオチを明かすのに「実は」を使うことに慣れていない頃、よく「これからどうなるでしょう」と結文していた子がいた。それを読んで、もしかしたらこの子の頭の中では自分なりの物語の続きがあるのかもしれない、きっと想像力の豊かな子なのだろうと感じられた。
またもや余談だが、以前、母にこんな話を聞いた。母は幼い頃、壺を抱えて飛んでいる蜂を見たことがあるのだそうだ。その時は幼過ぎておかしいとは思わなかったが、少し大きくなってから、「おや?」となり、以来ずっとあれは何だったのだろうと不思議に思っているという。それから更に歳月が過ぎたある日、私も同じ光景に出くわした。びっくりしてよくよく見直すと、壺と見えたのは何かの黄色くて大きい雌しべだった。私は長年の謎が解けて母がどんなに喜ぶかと急ぎ報告したのだが、思いのほか母の反応は「ふぅん」と薄く、拍子抜けしてしまったが、なんとなくわかるような気もした。長い間、自分の中で温めてきた記憶には、母なりの思い入れがあったのだろう。そしてそれは決して「実は百合の雌しべでした」なんてつまらないものではなかったはずだ。そんなことを思い合わせると、どの生徒も持っているだろうそれぞれの小さな世界をちゃんと見抜き、守りつつ整え育てることが、正しさより何より大切な講師の役割なのかもしれないと思えて、しかしその途方もない難しさにくらくらするのだ。