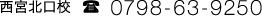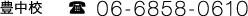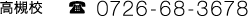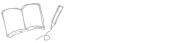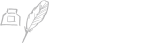2025.12.26Vol.80 「生きる」ためのアート鑑賞
大学生の頃、平田オリザ氏が講師を務める講義に出席していた。著名な劇作家でありながら演劇論を取り上げたことは一度も無く、芸術の受容のあり方について幅広く語ってくださった。そこでの平田氏の発言で記憶に残っているものが二つある。一つは、学生からの「地方文化の衰退の一因としてイオンモールを批判しているが、先生の著作である『幕が上がる』の映画版はイオンシネマで上映されているじゃないですか」と、意地の悪い質問をされた際に繰り出された「そうしないと資本主義社会では生きていけないからです!」という即答だ。「それで俺をやり込めているつもりか!?」という怒りが滲み出た正直な返事に、むしろ感心した覚えがある。そして、二つ目が「アートを前にした時、大人は価値を論理的に見出そうとするけど、子どもは感性的にしか捉えない。だから、子どものうちはひたすら名作に触れさせて審美眼を育むことが大切。成長するにつれて作品ごとの良し悪しを直感的に判断できるようになる。」である。平田氏が授業の流れを無視して唐突に熱弁を振るい出したのもあって印象に残っているのだが、子どもと接する仕事に就いてからはことあるごとに脳裏に浮かぶようになった。(一つ目のエピソードの方は「笑い話」の範囲を出ていない。)
今回の場合は、読み聞かせクラスで取り入れられている「アートマインドコーチング」がきっかけだ。社員講師は11月28日の体験会よりも前の会議にて、小西さんによるファシリテーションの下で「対話型鑑賞法」を実践する機会をいただいた。その際、ローザ・ボヌール (1822年-1899年)という女性画家の≪子牛の離乳≫(リンクから絵画の情報に飛べます)に対して、各人がタイトルを知らない状態で「絵の中でどのようなことが起こっているか」、「どのような音が聞こえるか」をじっくり探り、挙手制で発表していった。実は、私は初めて作品を目にした瞬間、画面の右手前にいるのはまさか若いライオンなのではないか、と戸惑ってしまった。濃い茶色の毛並みや、小柄ながらも引き締まった体つき、そして黄昏ているような表情から「たてがみが生えそろっていない獅子がサバンナの夕日を眺めている」というイメージと結びついたのだ。だが、周りの牧歌的な自然風景や成牛の姿が目に入ってくると冷静になり、最終的には「牧場に戻ってきたばかりの母牛を子牛たちが出迎えている」というストーリーを全員に共有した。面白かったのはここからだ。小西さんから「どこを見てそう感じましたか?」と、根拠を尋ねられたので、説明のために絵を見直してみたところ、自分なりに確定させたつもりの答えとは異なる可能性が開いてきたのだ。「成牛と子牛たちの目線が交わっていないな。お互いさほど関心が無いのかも。そもそも、なんで『母』牛だと決めつけられるのだろうか?」という風に己を疑い始めたら切りが無さそうだった。待ってくれている参加者たちを前に正直焦ったものの、画面奥から列をなして向かってくる牛たちの描写に着目すると、親牛が「帰宅」する場面だと捉えられると結論付け、何食わぬ顔でその旨を発言した。ただ、「自分では気づけていないポイントがまだまだあるに違いない」と客観視した上で他のメンバーの言葉に耳を傾けるためのステップになった。例えば、「柵が敷地を取り囲むための堅牢な造りではなく、長い枝と岩を活用した簡易的な物に思える」や「何頭かの牛は、絵の中には現れていない人間に視線を投げかけているのではないか」といった描写には、言及されるまで意識が向いていなかった。そういった要素が明らかになっていくにつれ、脳内にあるストーリーがバージョンアップしていくようだった。私個人は、「みんな」で協力しながら物語を作っているような感覚を味わっていた。
さて、プログラムが進むうちに、ある社員から「手前にいる子牛がライオンに見えちゃったんですよね」という声が上がってきた。奇遇なことに、私が自分の中で「ありえないもの」として切り捨ててしまった考えだ。けれども、同じような捉え方をした人が他にいた事実が嬉しかった。思わず「私もそうなんです!」と食いついてしまったのだが、その時も小西さんはただ微笑みながら根拠を聞いてくださった。我々の発言への評価も指摘も行わない。そのおかげで参加者は自由な発想を後押しされるし、迷いながらも紡ぎ出された言葉が「人の繋がり」を生むことだってありえる。「より良く生きていく上で重要な基礎能力が自然と育まれる」とはこういうことかと感じ入った。
冒頭で取り上げた「子どものうちはひたすら名作に触れさせて審美眼を育むことが大切」という発言に話は戻ってくる。学生時代の私は、我が子を有名画家の代表作の前に連れて行って「これ、すごい絵なんだよ」と声を掛けている大人の姿を思い浮かべていたが、そういった一方的なやり方では場がしらけて終わるだろうな、とも思っていた。今振り返ると、当時の私自身の「名作」と「アート鑑賞」の定義が狭量だったのだが。志高塾の読み聞かせクラスで扱われる作品も美術史的な価値は高い。しかし、大事なのはそこではない。選ばれているのは、情報としての豊かさを持ち、観る者の観察力や想像力を刺激する触媒として優れたものばかりだ。だからといって、作品を好きにならなくても構わない。ただ、対話型鑑賞に参加した人たちは題名と作者名を知らずとも、その絵を自ずと「名作」だとみなすようになるはずだ。