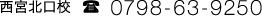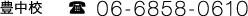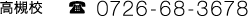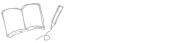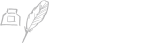2024.05.24Vol.23 修正過程(三浦)
文学館に行くのが好きだ。二月末、神奈川近代文学館に行くことを目的に横浜まで出かけた。神奈川は作家の療養地として人気の鎌倉にある鎌倉文学館もあり、本当はそちらも寄りたかったのだが、修繕工事のため休館中のことで断念した。いずれも既に一度は立ち寄ったことがあるのだが、会期によって展示が変わるのはもちろん、再訪するまでに読んだ作品が増えていると、こちらの見方もまた変わるというのが面白いところだ。ちなみに鎌倉文学館は日本遺産にも指定されている立派な建物で、入るだけでもじゅうぶん価値がある。
文学に精通しているわけでは全くないので、全く聞いたことのない作家の展示に当たることももちろんある。聞いたことがあっても作品を知らない、というのも同様だ。例えば今回で言えば大岡昇平の「野火」は聞きかじったことこそあれほとんど知らなかったのだが、一部分が展示されていただけだったものの、その一部分を食い入るように読んでしまった。同行していた知人はすでに読み終えていたので、知人の感想や解説も織り交ぜながら落とし込んでいった。
一番の目的は太宰治の展示だったのだが、そちらは原稿よりも手紙などのインパクトの方が強く、それよりも坂口安吾が書いた「あちらこちら命がけ」という色紙が思いのほか記憶に残った。言葉だけでは伝わりきらないのだが、のたうち回ったような、本当に命がけで何かを成していないと浮かび上がってこない筆致だった。以前は武者小路実篤の「君は君 我は我也 されど仲よき」の色紙に唸った。いずれも、作品と繋げて色紙を読むと、その人柄が色濃く反映されていて面白い。「心の底からそう思っていないと出てこない言葉だな」と思わせるものがある。
初版の装丁や直筆の原稿、色紙などを見るとどうしても胸が躍るたちである。基本的に文学館にはそういった直筆を見に行っている節がある。色紙はさておき、原稿には作者の悪戦苦闘が色濃く残る。細かな表現の修正を積み重ねた末に、最終的に普段読んでいる印刷物の形に落とし込まれているのだと改めてわかる。ものによっては版によって言い回しや内容が変わるものもあり、それを見比べるのも楽しみである。好きな作家は修正跡まで愛おしく見えるものだ。
ところで、Eテレに「ザ・バックヤード」という、博物館やテーマパークの裏側を取材する番組がある。その中で横手市増田まんが美術館が紹介されている回があった。私はその美術館について全く聞いたことがなかったのだが、秋田県にあるさまざまな漫画作品の原画などを保存・展示している美術館らしい。その番組内で印象的だったのは、原画に残る修正の跡である。インクで描いた上からでも、修正液(ホワイト)を使えば印刷時には修正されたことがわからない。だから印刷物を見ているだけでは、その絵が修正を重ねられた末のものなのか、あるいは一度で完成したものなのかはわからない。紹介されていたのは男の子が驚いているコマで、驚いている表現として口元のない、目元だけの描写になっていた。しかし原画をよく見てみれば、何度か口を描いては消し、最終的に「口元がない方がいい」として完成形としていることがわかる。他の番組にはなるが、手塚治虫の手書き原稿でも近しいことを紹介していた。要は、「いろいろ試した結果、これが良いと思った」という過程を見ることができ、そこから「なぜそれが良いと思ったのか」という狙いを考察することができるのだ。ただ、今はコンピューターを使った作品も多く、そういった作業過程が(データとしてはあるかもしれないが)目に見える形として残っているものは少なくなってきているのかもしれない。
修正の過程と結果、そこからその意図を読み取れるというのは、なかなか特別で貴重なことなのだと実感する。
思い返せば、志高塾の作文は修正の際に消しゴムを使わないことを原則にしている。生徒からはよく「なんでですか」と聞かれるのだが、そのたび、「どこをどうやって変えたのか、どう考えていたのかわかるから」と返す。初めからきれいに書けることより、より良くしようとして自分で手を入れたことの方が重要なのだ。そのため作文用紙は書き込みだらけになってしまうこともしばしばだが、読みにくかろうが問題はない、それもまたひとつの苦戦と工夫の証である。
この「志同く」も打ち込んでは消し、段落を変え、書き直し、そういった悪戦苦闘の工程を経て完成しているのだが、デジタルゆえにその過程は残らない。残ったら多分とんでもないことになっている。その修正の多さは、やり直しが容易なデジタルだからこそ、かもしれない。一長一短、一手一手に意味を込めた修正は、アナログの特権でもあるのだろう。