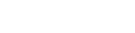1,中学高校時代
私は小中高一貫の学校に通っていた。小学校6年次の4月に「起立性調節障害」と診断され、その後中学に入学してからも体調によっては2限目から行ける日もあるものの、平均すると4限目から行ける程度で授業への出席はあまりできていなかった。中学3年生になると、高校で通信制に行くことを考え始める。しかし、授業には出席できていなくとも、宿題や課題の提出を欠かさずしており、学校のテストでも平均点以上を取っていたため学校の先生には高校に上がることを勧められた。その勧めに従い、とりあえず進学することを決める。
しかし、コロナが直撃した高校1年次の春、学校に通うことに体力を使い果たしては大学受験ができないと判断したため、1年次の1学期で退学した。通信制の高校もいくつか訪れてみたが、私は不登校に分類される中では自分で勉強をしていたため、進度が合う学校が見つからず、高卒認定を取得し個別の進学塾に通う判断に至った。
その後、高校1年次の秋に高卒認定を取得し、医学部を目指し勉強に励んでいたが、高校2年次の1月にまた体調を大きく崩し、志望校を慶應義塾大学SFCに絞ることに決める。医学部に行った場合は精神科医になりたいと思っていたため、文転に伴って分野の近い心理学部に強い大学を調べることにした。その中でSFCでは脳科学の勉強ができると知り、心理学と脳科学を組み合わせて勉強したいと思った私はSFCを第一志望にしたのであった。
SFC受験にあたって小論文と英語のレベルを大幅に上げることが必要となり、高校3年次に該当する年の4月に小論文対策をしてくれる塾を探し始める。しかし、関西にはSFCの特殊な小論文の対策を引き受けてくれる塾は中々なく、途方に暮れていたところ、母の友人の紹介で志高塾に通うこととなった。
2,志高塾で育つ意識
以降は週に2回の個別塾と週に1回の志高塾が私の生活のリズムとなる。小論文の勉強にあたって、ただ問題を解くだけではなく、前提知識になるような本を勧めてもらったり、テーマについて自分の考えを先生と話したりする時間がとても楽しかった。志高塾に通い始めてまず大きく変わったのは私の「意識」だったように思う。普段から色んな分野にアンテナを張り、世界情勢やニュースをチェックして、本を沢山読み、などと見聞を広げようという意識ができたように思う。先生と話していると自分の知っている知識の狭さや浅さを痛感し、もっと深く色んなことを知りたいと思うような知識欲が強く沸いた。もっと沢山の知識をつけてもっと深い考えを先生と議論したい、文章で表現できるようになりたいと自然と思うような空間であった。友人や家族と中々しないような社会情勢などのテーマについてじっくりと考えている時間は、普段の生活では使わない脳の部位が働いているような気がした。より深く考える習慣がつくまでは考えることや集中することが難しいが、毎週小論文に向き合う内に楽に思考できるようになり、まるで脳の筋トレをしているようであった。志高塾で学んだのはただ小論文を書くテクニックなどではなく、自分の思考の癖を知り、視野を広く持ち多角的に物事を考えるということだと思う。このことは受験だけでなく、これからの人生を生きていく上で必要な能力である。
大学に入ると、レポートの課題が沢山出されるようになる。志高塾で小論文を沢山書いたおかげで、周りに比べると苦労することなく書けているように思う。パソコンでレポートを書くようになり、ChatGPTなどの生成AIが身近になった今、テーマを打ち込むだけでそれなりの文章を書いてもらうこともできるが、人間だからこそ紡ぎだせる文章力や国語力を持っていたいと私は思う。
私は今、高校生の頃に憧れたSFCの脳科学の研究会に所属し、情動の研究をしている。所属するものがないことや、あまりにも自分次第の未来に不安を抱えて日々を過ごしていた中高時代の私には現在の生活は想像もできなかっただろう。今があることは、自分の努力と私を指導してくれた志高塾の先生や学校の先生などの周りの大人達、そして努力できる環境を与え、私を信じてくれた親のおかげである。
受験や将来のことで悩み、不安定な時にいつも志高塾の先生は指針になってくださった。自分一人でもがいている時に、一緒になって道を考えてくれるような温かい大人が私には必要であったし、誰でも不安定な時期には道を示してくれる大人が必要だと思う。また、同じような背景や状況の中にいる人にとって私の存在が少しでも勇気になればと思う。