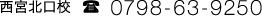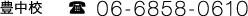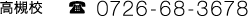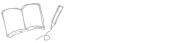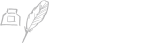2026.02.27Vol.86 輪を広げる(徳野)
昔から人の輪に入っていくのが下手だ。赤ん坊の頃から何事も平均よりワンテンポ遅い人間だったらしいが、成長後も集団内の「ノリ」に乗れないまま今に至る。ただ、高校生まではそれでも困らなかった。兄弟姉妹がいないのもあって一人遊びには慣れているし、趣味も相手がいなくても成立するもの(音楽と映画の鑑賞、読書など)ばかりなので、毎日をマイペースに過ごせれば十分に楽しかった。何より、高校まではスケジュールを勝手に決められていたようなものだ。極端に言うと、授業を受けたり、好きな本を読んだりするために机に座っているうちにいつの間にか一日が終わっていた。当時の人付き合いといえば、たまに話しかけてくれる優しいクラスメイトたちと5分ほど言葉を交わす程度だった。こうして振り返ると、身近な他者に興味を抱かず、色々な事に対して受動的だったのが一番の問題だ。さらに、自分の傾向を「問題」と認識しないまま大学生になってしまった。就職活動が迫ってきてようやく慌てているようでは遅い。そんな私が、個別指導で、しかも会話量が多い志高塾で講師をしている。人生はどう転ぶか分からないものだ。そして、社員になってから強く感じていることだが、今の仕事をしていなかったら両親ともまともに関わることなく、最悪、短い一生を終えることになっていた気がする。
ここまでの流れだと、私の性格が変わったかのような印象を与えるかもしれない。そんな訳はない。いわゆる自己開示が苦手で、授業外で誰かと一緒に過ごしたいという気持ちが湧くことは今でも滅多に無い。ただ、前と違うのは、現状のままでは良くないと捉えるようになったことだ。なぜなら、人間関係の構築から逃げ続けてきたせいで、仕事においても、他者との繋がりを広げるための行動の価値をきちんと理解できていない節があるからだ。その旨をSNSで述べたら「公私を分けたほうが良い」、「仕事のために人付き合いするなんて不自然だし利己的だ」などの声が飛んできそうではあるが、そういった正論が私の場合は自分への甘やかしにしかならない。ありがたいことに「大学受験が終わったら先生と美術館に行きたい」と言ってくれている高校3年の女の子がいるので、こちらから連絡をしようと思う。また、文化人類学に興味がある彼女には辺見庸の『もの食う人びと』や松村圭一郎の『うしろめたさの人類学』といった本をお薦めしたい。(後者は教室にあるのに加え、複数の講師が面白い作品として取り上げていた。)
「繋がり」という点では印象深い卒業生がもう一人いる。志同くVol.41にも登場した、大阪大学基礎工学部3回生のF君だ。相変わらずXでの発信に意欲的で、現在は「ナウルにフォロバされている代表お出かけスポットサークル代表(https://x.com/1IeqedjfwucuPu2?lang=ja)」という情報量がやたら多いアカウント名で活動している。しかもnoteも始めている。恐ろしいことに2,000字程度の文章をほぼ毎日投稿しているのだから畏怖の念すら湧いてくる。
そんな彼には、去年の夏にホームページに掲載する「卒業生の声」の執筆を依頼してみたものの、本名と顔写真をインターネット上に公開することへの懸念があるとのことだったため見送ることになった。当然ながらF君には何の非も無いのだが、この年明けに「お力になれず申し訳ありませんでした」という旨のメールをわざわざ送ってくれた。こうなったらnoteにて志高塾で過ごした時間について綴ってもらうしかない。お願いしてみたところ、その2時間後には「志高塾についての思い出(https://note.com/fast_otter5441/n/n7ea382817688)」がアップされていた。「言い換えること」の大切さを学生目線で述べてくれているので、本人の励みになるよう、URLを検索して是非読んでいただけると幸いです。また、個人的には「入塾してからは、作文が以前よりも好きになっていた。もちろん、常に順風満帆というわけではなかった。特定のテーマについて作文を書くとなって、どう書けばいいのだろうか、とかなり悩んだこともあった。しかし、先生方からのアドバイスとかで、『こういう考え方もあるんだ』とか『こう表現したらいいんだ』といった感動もあった。新たなモノの見方など、中学2年生の冬までにはなかったものが、今の自分にはあるのだ。それは、全てそうというわけではないが、志高塾のおかげでもある。」という段落にほろりと来てしまった。上記の紹介文が公開される前に彼の文章を他にも読んでみたのだが、通塾当時には希薄だった「自分が取り上げたテーマに馴染みの薄い人に向けてどう伝えるか」という視点が窺えた。不特定多数の相手に向けて「お出かけスポット」の魅力を発信する活動を通して身に着けたのだろうな、と感心していたのだが、F君本人が志高塾での取り組みと自身の成長を結び付けてくれていることには感謝するばかりだ。
さて、F君のXとnoteを見ていると、青木悠(あおき はるか)さんという大学生と、彼女の著作『京大生、出町にダイブ! 京都下町見聞録』への言及の多さが目に付く。どうやら青木さんの存在がF君の執筆欲を高めている様子だ。何が彼を搔き立てるのだろうか。そんな好奇心からエッセイ本を手に取り、現時点で3分の2ほど読み進めている。まず、描写力がとにかく素晴らしい。青木さんは高校では演劇の脚本を手掛けていたとのことなので書くことにはかなり習熟しているのもあるのだろうが、舞台となる商店街のカラフルな光景と空気感が驚くほど丹念に、そしてまっすぐ言葉に落とし込まれている。読者の私まで昭和の風情を残したアーケード街を本当に歩いているような気分を味わえる。同時に、読んでいるだけでは飽き足らない、という感覚も呼び起こされた。作中には「出町びぎん」という喫茶店が頻繁に登場する。一人暮らしをする青木さんにとっては第二のホームと言えるのだろうし、多くの常連客にとっても単なる「美味しい飲食店」に留まらない意味を持っているのだろう。それくらい金銭のやり取りを超えた人どうしの密な交流が続く、令和の今となっては稀有な場所である。しかも府外からの若者が溶け込みたくなるような寛容さも持ち合わせている。その雰囲気を肌で感じ取ってみたい。青木さんも初めての入店時は緊張したそうなので、私はそれ以上に二の足を踏みそうな予感がしているが、彼女に背中を押されていると思って実際に足を踏み入れてみたい。この春休みは、出町桝形商店街も含めて少しニッチな京都旅行をすることになる。
2026.02.20社員のビジネス書紹介㉙
三浦のおすすめビジネス書
鈴木義幸 『承認(アクノレッジ)」が人を動かす』 ディスカヴァー・トゥエンティワン
前回ここで取り上げた、「コーチングが人を活かす」の著者の本だ。
承認、アクノレッジ。それは単に相手を評価するというのではなく、相手に「自分はここにいてもいい」と思ってもらうことだ。承認されることの安心感は想像できるが、それが人という「社会で生きる動物」にとって、自分が仲間の一員と認められないことは死を意味しているから、というのは納得がいった。集団で生きることが基本の人間にとっては、「存在が認められない」こと自体が多大なストレスになるのだ、と。だから相手の存在を承認し、安心感を与えることが大切なのだと。
生徒に対して然り、他の講師に対して然り、「相手がいてくれて嬉しい」というのはごく当然の感情として常に存在する。しかし、それをうまく伝えられているかというとそうではない自覚もあった。例えば「相手の結果を褒めるのではなく、相手の過程を評価する」「相手の行動をまずは観察し、それについて言葉にする」というのは、生徒に対してよく行っていることだ。ただ、本書には「相手がどう言って欲しいのかを考える」とあり、当たり前のことなのに、そこに思いが至っていなかったことに気が付いた。本書で取り上げられている例を見ていると、それは言葉の面でもあり、そして伝え方の面でもあると思った。目を見て、ゆっくりと、相手に心が伝わるように話す。私は多分、大切なことを話すことに慣れていない。もっと練習する必要がある。
また、「YouではなくIで承認する」、つまりは相手がどうしていたかだけでなく、「相手の行動が自分にどう影響を与えたか」を軸に評価するほうが、相手にとってはより大きな承認となることが多い、という内容もあった。思っていることは同じでも、伝え方や視点によってまったく受け取る印象が違う。文章を書く際には意識しようとしていても、話すとなるとすっかりそんなことが頭から抜け落ちてしまう。無意識にできるようになるまでは、やはり、練習あるのみなのだろう。
徳野のおすすめビジネス書
ジョン・ムーア 『スターバックスはなぜ値下げもCMもしないのにずっと強いブランドでいられるのか?』 ディスカヴァー・トゥエンティワン
志高塾の、特に国語の授業料は高いと思う。最近強く実感させられたのが宝塚音楽学校付属の「宝塚コドモアテネ」の月謝を知ったときだ。月額15,000円で毎週日曜に約5時間、声楽とバレエと日本舞踊の3科目の指導を受けられるとのことだ。一方の我々は週1回90分の授業で(現在は)26,000円をいただいている。コドモアテネの生徒には稽古着や教材などのために別途の出費も求められるはずなので、トータルで見れば毎月の支払いは15,000円では済まないだろうが、志高塾に通い続けるにはトップスター候補になるよりも多くのお金が掛かるかもしれないのだ。ただ、そういう風に表面的な数字ばかり比べていても明るい気分にはならない。(現時点で)26,000円という金額に対して、保護者様と講師の両方にとっての納得感を生むために必要な視点を学んでおくことにする。
スターバックスがコーヒーの価格を高めに設定しているのは、使用する豆の品質を維持するである。それが象徴するように、提供する商品とサービスそのものへのこだわりを第一に考えていることが同社の競争力の高さに繋がっている。当たり前ことをしているだけのように思えるかもしれないが、米国に本拠地を構える他のチェーン店は「低価格」と「大規模なプロモーション」を基本戦略としており、それらはスターバックスが意図的に避けている方向性である。バーゲンセールやキャンペーンを多用しての薄利多売と、実態から乖離したブランディングは、ひどい場合は1週間も経てば現場の士気低下と売上の減少に終わることが多いからだ。長く愛される企業になるためには、消費者の目先のニーズに最適化するだけでなく、顧客の「ウォンツ」を叶えなければならない。ウォンツとは癒されたり好奇心を刺激されたりするような「より良い状態」への願いを指しており、スターバックスは、清潔な店内で多彩な産地から取り寄せた本格的なコーヒーを味わいながら人と触れ合う「エクスペリエンス(体験)」を提供することで実現を目指す。そして、理想主義的であるのと同時に、顧客からの要求を受けた際には、それが会社の理念に沿っていると判断すれば慣習を変える柔軟性も大切にしている。例えば、イタリア式の伝統的なカフェラテは必ず有脂肪乳で作られるものの、カロリーへの意識が高い都会の住人の中には無脂肪乳への変更を希望する人も少なくなかった。こだわりの強い(悪く言えば排他的な)バリスタなら断ってもおかしくないオーダーだが、スターバックスは米国の大企業らしくカスタムの一種に組み込むことでリピーターの幅を広げてきた。
学習塾が提供するのは形の無いサービスだが、それが「エクスペリエンス」の域に達しているかどうかを決めるのは生徒と保護者である。また、学生にとってのニーズとは入試を含むテストの点数になるだろう。だからといって、高校生相手を例にすると、模試の成績や大学名を元に何となく決められた志望校対策を漫然と行っていては貧相な経験しか生まれない。AIが勉強の相棒になる時代にわざわざ教室に足を運んだり、オンライン上で講師と対話したりするのだから、一人ひとりに対してまずは「あなたは高校卒業後に何をやりたいのか、どうありたいのか」という根本的な問いに一緒に向き合える場であることは、志高塾の魅力となる「カテゴリー」だと確信している。
竹内のおすすめビジネス書
今井孝 『いつも幸せな人は、2時間の使い方の天才』 すばる舎
何となく時間に追われているような気がして焦ることも、こんなに時間があったのに何もできなかったと落ち込むことも、自分の日常には多々ある。1日を生きることの下手さには我ながらうんざりする。そういう日々を立て直すために、まずは「2時間」を丁寧に見ていくことから始めたい。その切り口は色々ある。
まず、日々を過ごす中で自分を満たしてくれるものは何か。それがある1日と、ないまま終わってしまう1日では充実感は大きく異なる。もちろんそれがいつも同じことである必要はなく、むしろたくさん引き出しがある方が、良い一日だったと感じられることも増える。自分をケアするための時間を生み出す、そのためにもまた何に2時間を使っていくのかを考えていかなければならない。スケジュールの見直しに2時間かけることも、そこで集中してこれと決めたことを終わらせることも一つである。
また、かけた2時間をきちんと評価することも、継続していくためには欠かせない。成果物という形になったものがなかったとしても、それをゼロと片付けてしまうのか、構想は練られて20%くらいは進んだと取るのか、そこを正確に捉えることで、翌日に何から着手すべきなのかも明瞭になる。ゴールに向かって道を進んでいるという自覚がないと、状況を確認する意識は薄れてしまうのだ。私はそのようなマイルストーンを置き忘れてしまいがちだし、もっと言えば置けるような時間の使い方になっていない。まずは頭の中に浮かべるだけでなく、それを言葉にして残す時間を作ることとする。
2026.02.13Vol.85 たいせつな曲線(三浦)
高校時代からずっと同じ整体院に通っている。高校生の時に姿勢の悪さやその他諸々が原因で、右足首が非常に痛むようになり、それを治してもらいにいったことがきっかけだった。学校ではちょうど持久走の時期で、診断書と共に先生に掛け合い、どうにか歩いて最低限でも出席と評価をもらおうとしたものの、それまでの欠席が響いて単位を落としたことを未だに覚えている。あとは足首の痛み自体より、不自由なせいで階段にぶつけてつま先を出血した方がショックだったことなんかも印象的だった。というか、姿勢の悪さで足首にダメージがいくのかと、その点もなんだかショックだった。
人の身体の癖というものはなかなか治らず(癖や歪みはあっても仕方ないらしい)、それ以降の付き合いになる。もうかなりの年数を通っていること、そして親子ともども世話になってきていることもあって、先生ともそれなりに懇意にしてもらっている。大学生くらいまでは「背骨と骨盤がおかしいことになっているね」と月に一度くらいは矯正してもらっていたのだが、最近は「そこまでおかしいことになっていないね」と、ふた月に一度メンテナンスに行く程度に収まってきた。ようやく少しずつ身体がうまく使えるようになったのかもしれない。大学時代までに比べれば健康面でもかなり良くなってきているので、成長にともなって少しずつ体力がついてきたのだろう。
とはいえ身体の緊張は昔からあまり変わらないので、夏期講習や受験などの大きなイベントごとの前後にはよく世話になる。自然と会話もそういった話になり、勉強や受験のこと、そして大学のことなどの話題が施術中にのぼるようになる。塾にいると感覚がわからなくなることも多いが、「受験」というものの必要性をさほど感じない人も世の中にはもちろんいて、先生がそういう人だった。
「大学でやったことって仕事に生きてるん?」
その折によく問われることなのだが、いつもどう答えたものかと考える。私個人としては「じゅうぶんに生きている」のだが、それが世間一般的だとは思わない。
私は文学部の、特に日本文学の専攻だった。リベラルアーツとして他の基礎の講義も受講はしたものの、やはりメインは日本文学研究である。一般的な仕事ではたして生きるだろうか。私からすると、そんなことはないと思う。文学史や文士の人生が、そのままビジネスに使える気はしない。エッセンスとして生き様を取り上げたり、格言を座右の銘にしたり、歴史の中に活路を見出したりはできるだろうが、直接的なものではないだろう。
そう思うと、私の場合はかなり特殊だ。国語の塾講師。研究職を除けば、これほど専門的に文学のことが役立つこともあまりないだろう。なのでいつも、「私の場合は役に立っているけど、他はそうでもないんじゃないかな」というやんわりとした答えになっている。
世間話としてはそこで終わってもいいのだろう。しかし、例えば大学受験前の生徒に同じことを問われたときにも、同様の答えで終わらせていいのだろうか。特に文系の分野においては、よく、仕事から逆算して学部を選ばないようにと伝えている。就職先のグラフなどを見ていると、とてもではないが直結しているとはいえない学部の方が多いからだ。私の数少ない同学科の友達を見ても、冠婚葬祭業界や食品業界、あるいはゲーム業界への就職と、なかなか多岐にわたっている。ただ、逆に言えば「文学を研究していても、そういった職に就ける」のだ。あれだけさまざまに「なんの役に立つのか」と言われている文学でさえも。
そう考えると、「大学での学びは仕事に生きるのか」という問いの答えは、やっぱり「あんまり関係ないかもしれない」「生きてはこないかもしれない」、になるのだろう。でも、「大学での学びがその先の人生に生きるのか」という問いであれば、「いつかは生きることもあるし、生かしようもある」と答えられる。例え私はこの職についていなかったとしても、文学館を目的に遠方に足を運んでいただろうし、その時に受けた大学の講義に思いを馳せていただろう。あるいは論理学が壊滅的にできずに単位を落としたことが影を落として、やり直してみようと思い立っていただろう。世間話に講義の知識がのぼることも、もちろんあるだろう。
直接的に、まっすぐ、その先の人生に繋がることは少ないかもしれない。でも、それこそじっくりと時間をかけて、何かが芽を出す日が来るだろう。体がすぐに矯正されることがないように、思考が変わるにも、知識が根付くにも、きっと時間がかかるのだ。そんな長いスパンで人生を捉えられるのか。それは難しいけれど、短い捉え方だけになってしまわないようにしてあげたい。
2026.02.06Vol.84 レシーブ(竹内)
去年の6月から、この「志同く」に各教室の講師による文章を掲載してきた。もともとは私が担当していた回を、我こそはと名乗り出てもらったり声をかけさせてもらったりして先月までで8名に登場してもらった。松蔭のものはもちろん社員ブログも含め、これらは「志高塾で教えている講師」一人ひとりがどのような人物であるのかを、このページまで来てくださった皆さんに感じ取っていただく場である。普段勤務している教室の違いで日頃の関わりの濃さにはグラデーションがあるが、各人の姿を浮かべながら読むそれらからはその人らしさや意外な一面が感じられ、共感することも、問われることもあった。そして、このような場でやはり自分自身が書くことを積み重ね、このページを開いた方々に届けていかなければいけないということとも向き合った。
この期間の最後を飾る9人目は、今年度限りで卒業する豊中校の学生講師にお願いした。彼女をはじめ、文章を寄せてくれた講師たちから得た刺激を、これからに繋げていきたい。
志高塾での6年間を通して「どうして6年間続けられたのか」
6年と聞いて、長いと感じる人の方が多いのだろうか、短いと思う人もいるのだろうか。ひとによるだろうし、ものにもよるだろうが、私にとっては、ひとつの仕事を続けた年数としては「長い」と感じる。だが、今この期間を振り返って「長かったな」とは感じない。あっという間だった。気づいたらこんなにも続けていた、という感覚だ。心理学の授業で、つまらない時間は長く感じるが楽しい時間は一瞬で過ぎ去る、と聞いたことがある。6年が一瞬だと感じた私にとってここでの時間は「楽しい」ものだったのだろうか、それとも他にどんな感情があったのだろうか。
メールの履歴を遡ってみると2020年2月20日に選考結果のお知らせが届いていた。3月4日から勤務開始、ということだった。私はここの卒業生ではない。だから、ここに入る前から特別な愛着があったわけでも知り合いの先生がいたわけでもない。それでもなぜ、他の個別塾ではなくここを選んだかといえば、国語が得意だったからである。正確に言えば、国語が得意に「なったから」である。私はもともと国語が苦手だった。そうは言っても、学校のテストはそれなりに点数が取れていた。なぜか。丸暗記が可能だったからである。学校の中間試験や期末試験では必ず出題範囲が決められていた。授業で扱った教材について先生の主張していたポイントをおさらいしていればそれでOK。古文の単語や漢字の問題も直前に呪文のように唱えまくって寝れば、翌日のテストではほぼ満点を取れた。そういった意味では記憶力だけは良かったといえるかもしれない。こういう“得点源”で稼げていたから、結果的にそこまで心配するほどにはなっていなかったし、そこまで危機感も抱いていなかった。それでも私は国語が苦手だった。それが如実に現れたのは、実力テストだった。これが厄介なことに、さきほどの学校の試験と違って“得点源”が無いのである。事前に対策のしようがない。とても困った。仮に勉強しようと思っても、国語の点数を上げるために何を勉強するのか、私にはわからなかった。「国語力が無い」そのことにいつ頃気づいたか、あるいは気づいても気づかないふりをしていたかもしれない。だって、気づいたところでどうすればいいのかわからないのだから。
そんな私にも受験期が訪れた。否が応でも勉強するし、国語に関しては参考書や予想問題を解きまくった。最初の頃はやはり成績不振だった。記述問題では本当に伸び悩んだ。他でカバーするか、と思いつつそうできるほど他教科も余力は無かった。それでも、なんだかんだ勉強していたら、急にできるようになった。でもここに再現性はない。自分でも何をしたのかわかってないから。どうやって成績をあげたのか、と聞かれてもわからない。でも、得意になってから気づいたことならある。国語が伸びると、伸びるのは国語だけではない。どういうことかというと、英語ができるようになった。特に英作文が得意になった。知っている英単語が増えたからではない。知っている単語の範囲で書けるように要約・言い換えをする術を身につけたからである。「要は、何を伝えたいのか」を掴むことができるようになれば自分の英語で表現できる幅は意外と広かった。この「要点を掴んで言い換える」は何も日本語から英語に限られた話ではなく日本語から日本語、つまり国語の記述問題でも同じであった。限られた字数の範囲内で自分が何を伝えたいのかを考え、字数が足りなければ要点を残して簡単に要約あるいは言い換える。たったそれだけのこと、と思われるかもしれないが、私はそれを理解し習得するのに数年かかった。また、自分の伝えたいことを考えると、逆に相手が何を言いたいのかがわかるようになった。振り返ってみると、こうやって表現することと読解することとの行き来を繰り返して国語力をつけていったのかもしれない。中学生くらいまでは、それっぽいところを解答欄で継ぎ接ぎして字数に収めればそれでいいと思っていた。でも実際に必要だったのは、自分の伝えたいことを字数の範囲内でどのように盛り込むかを考えること、そのために、自分の言葉で言い換えることだった。それには語彙が必要だ。だから自然といろんな単語を使うようになった。この頃のコミュニケーションはとても楽しかった。自分の言いたいことを的確な単語で表現して伝えられることがこんなに素敵だとは思ってもみなかった。一方で、コロナ禍に入って驚いたのは、あれだけ自由に使えていた単語たちも一時期コミュニケーションが減って使わなくなっただけで、途端に自分から言葉として出てこなくなることである。継続的にこの部分の脳を使っていないと、すぐ使い方がわからなくなるのだ。
この塾にきて驚いたのは、私が受験期で学んだことを、教えていたということだ。どういうことが言いたいのかを考え、伝えたいことをどうやったら上手く相手に届くのかを考え、さらにそれを自分の言葉で言い換えて表現する場所。自分も受験までにこの塾に出会っていたら、国語はもう少しまともだったかもしれない。私がここで6年も働き続けた、その答えはここにあると思う。私は、ここでの生徒たちに過去の自分を投影していたのかもしれない。自分が学びたかったこと、やっておきたかったことがこの塾にはある。どう頑張ったって、昔の自分がここに通うことはできない。無駄、とは思っていないが、もっと早くここに出会っていればあんな苦しい時期を過ごさなくて済んだ、そう思うことがある。そう、きっと私はこの6年のあいだ、生徒たちを通して昔の自分を見ていたのだ。こうすればいいよと、自分を導く代わりに生徒たちにそれをしていたのだと思う。かつて、「言い換えって何の意味があるんですか」そう言った生徒がいた。私もその立場ならきっと同じことを考えた。何に役立つかわからないことに労力と時間を費やすのは酷だ。「自分の言葉で表現する」と言われても、解答欄は本文の内容を継ぎ接ぎして埋めればOK、と考えている自分(あるいは生徒)からすれば、わざわざ別の言葉に直す手間をかけるのは面倒だ。それでも、言い換えてみるように促していたのは、今の私が、いつかその力が必要になるとわかっていたからだ。私みたいに困らないように。それで過去の私が報われるわけではない。けれど、今、目の前にいる生徒に向き合うことは、今の私を救うことになっていた、のかもしれない。おそらく今ここに通っている子の大半は、何となく通っていると思う。考えるのは疲れるし、眠いし、他のことに時間を割きたくなる気持ちもわかる。わかっているようでわかっていない、今はそれでもいいだろう。今はその価値に気づいていなくてもいい。なんでこんなんやらなあかんねんと思っていてもいい。でも、いつか必要だと分かったときのために、今、頑張ってほしいと願う。
受験もコミュニケーションも、結局は国語力である、と、私は考える。もう少し早く出会えていたら、とは思う。でも、人生は必要なタイミングで必要なものと出会うらしい。出会えて良かったと心から思う。
2026.01.31Vol.83 自信と謙虚のあいだ(徳野)
小学生の頃からドキュメンタリー番組が好きだ。これまで見てきたものの中で印象に残っている一本を問われたら、≪情熱大陸≫の世界的なヴァイオリニストの庄司紗矢香に密着した回を挙げる。調べたところ19年前の放送だった。時の流れはおそろしい。それでも記憶がある程度の新鮮さを保っているのは、庄司氏があまりにも気風の良い女性だったからだ。彼女はパガニーニ国際コンクールで史上最年少の16歳で優勝したことで、スター演奏家の仲間入りを果たした。しかもこのコンクールは「1位該当者無し」が珍しくないくらい審査基準が厳しい。そして、番組内ではおそらく表彰後に行われた記者会見の様子が一部流されたのだが、記者から感想を尋ねられた庄司氏は涼しい顔で「優勝すると思っていたけれど(実際に1位を獲れたのは)やっぱり嬉しいです」と返していた。なんてクールな発言だろうか!放送当時9歳だった私は、彼女のように堂々と自信を持っている日本人を目にしたことが無かった。優秀な子や才能のある子じたいは身近にもいたし、彼、彼女たちの性格もそれぞれであったが、自身が力を入れている分野の話を学校の教室で持ち出すようなことはしなかった。また、一芸に秀でていようがいまいが「自分なんて大したことない」という謙遜のポーズを取ることが良識なのだと、大人たちからは教えられてきたし、子どもたちの方も集団生活を送る上で重要な処世術だと肌で理解していた者が大半だったはずだ。空気を読むのが下手な私でも、出る杭になっては生きづらいだろうとは感じていた。そういう常識の下で生きていたのもあり、10代ですでに一流の精神が確立されていた庄司氏の姿は衝撃的だった。プロフェッショナルとは、自分の立ち位置を正確に把握しながら、ゴールの無い研鑽の道を歩むことができる人物なのだと教えられた。また、努力を続けられているのは、目標を達成した喜びを純粋に受け止める素直さもあるゆえだ。数値化が難しい音楽の領域において己を客観視できる鋭い感性は生まれ持った素質によるのだろうが、トップランナーに対して「天才はやっぱり違うなぁ」という漠然とした尊敬を抱くだけで終わるのは勿体ない。彼ら、彼女らの活動に触れることの意味は、凡人なりに「より良く在る」ための視点を与えてくれることにある。
庄司氏の発言が最近になって脳裏に浮かんだきっかけは、国語講師に応募してきた方の面接を通して、相手は「作文が得意です」と(たとえ表面上でも)断言するまでに葛藤はあるのだろうか、という疑問が湧いてきたことだ。私の知る限り、著名な職業作家は作品に誇りは持っていても、だからといって「執筆が上手いです」とはアピールしない。誰よりも言語化能力と構成力に長けているのに。だが、言葉を大事にする彼、彼女らが「自分なんて大したことないんです」などと表面的な謙遜をするはずは無いだろう。
肩を並べるようであまりに恐縮なのだが、私自身が「得意」という自己認識を持っていない、より正確には「持ってはいけない」と肝に銘じている。これまでの「志同く」でも今となってはぞっとする内容のものを掲載してしまったのは一度では無い。逆に、他の講師から有難いことに高評価を貰えた場合でも、実態は「全然きれいにまとめられなかった」と半ば絶望しながらのブログ更新だったりする。要は、当の書き手にとっても文章の質は発表してから決まる部分があるからこそ悩む。掴み所の無い相手との格闘のようなものだ。ちなみに、あの村上春樹氏は空想上の「うなぎ(の蒲焼)」と協力しながら闘っているらしい。彼いわく、小説とは、筆者と読者とうなぎが「三者協議」を行わないとが生まれないものだという。私は内田樹氏の著作『先生はえらい』での引用文を通して村上氏の創作の裏側を覗いたのだが、第三者的な視点をうなぎのキャラクターに設定している理由は明かされていなかった。内田氏は「それを嫌う日本人はほとんどいないけれど、(産卵場所のように)謎に包まれた部分も多い」点が比喩表現として秀逸だと評価しているため、一般論を想定して物語を練るという意味なのだろう。つまり、「伝えたい」という衝動に任せてただ好きなように書き連ねていては、かえって伝わらない文章が出来上がってしまう。そして、「志同く」の場合に引き寄せて考えると、テーマに自由度に甘えることなく、日常生活で琴線に触れた事柄について「ここから生徒と親御様が何か気づきを得られる内容になっているか」を見直すことと繋がっているのではないか。
面接の話題に戻る。応募者は国語の専門塾と自分をマッチングさせるべく「得意です」とあえて言い切っている面もあるだろう。ただ、もう少し踏み込んで、国語に対してポジティブな気持ちを抱くようになったきっかけを教えてもらうと、「何気なく書いた作文を大人に褒めてもらえたから」や「入試科目の中で一番点数が良かったから」という答えが返ってくる。それらはご本人の自信に繋がる大事な経験だろう。ただ、個人的には、苦しみの過程を経て「作文を好きになった」もしくは「今でも得意ではないけれど重要性を認識するようになった」という結論に至っている人の方に魅力を感じる。言葉を紡ぎ出すことの困難さに正面からぶつかってきたがゆえの謙虚さが滲み出ているからだ。
2026.01.23社員のビジネス書紹介㉘
三浦のおすすめビジネス書
鈴木義幸 『新 コーチングが人を活かす』 ディスカヴァー・トゥエンティワン
まず印象的だったのは、自分自身へのコーチングともいえるマインドセットについても都度触れていることだ。コーチングとは用意した答えに相手を導くのではなく、「相手なら何かを見つけ出せる」と信じて問いを投げかけ、一緒にその答えを深めていくものだとしている。その「問い」は、自分自身に投げかけてもいい。例えば対人関係で悩んでいるのであれば、その気になっている相手に対する質問をいろいろと考え、その人になったつもりで答えてみる。これによって相手の立場に立つことができる、というものだ。目標設定に関しても、漠然としたところから質問を重ねることで少しずつ具体化していき、最終的にはそれをもう一度抽象化するという流れを、一人で行うこともできるのだ。もちろん、誰かと対話しながら行う方が理想的ではあるだろうし、それがコーチングなのだろうけれど。
また、生徒とのやり取りにも通じるところがあった。どうしても答えやこちらの考えを先に言ってしまいたくなるものでもあるが、そうではなく、まずは相手の力を信じて、切り口を変えながら問いかけを続けて行くことが大切だ。とはいえ、それは相手に丸投げすることではない。指導の際には、自分なりにある程度の見解を持っておきながら、相手が自分の力で何かに辿り着くのを最優先させる。自分の思う何かがたったひとつの答えではない、その当たり前のことを肝に銘じておきたい。
最後にもう一つ。どうしても行動を習慣化できないと悩んでいたのだが、本書でそれは「行動の過程を考え、その苦労を想像していやな気持ちになっているのが原因」、「過程ではなく結果を思い浮かべるといい」と述べられていた。まさかコーチングの本で出会うとは思わず、だからこそ印象深かった。
竹内のおすすめビジネス書
杜師康佑 『超凡人の私がイノベーションを起こすには』 日本経済新聞出版
これが「タイトル買い」というものなのだろうか。
革新とは一握りの天才によるひらめきで起こると考えられがちである。いや、アイデアが出てこない自分に対して、そういうものだと思いたくなってしまうというのが正しいかもれない。しかし日経新聞で長くビジネス関連の記事を書き続けてきた著者にとっては、社会を変えていく新しい製品やサービスは、降って湧いてきた発想によってではなく、挑戦と失敗を繰り返して誕生するものなのである。本書では、これまで取材した数々の企業の実践例を取り上げるのはもちろんのこと、仕事と並行して慶應の大学院でシステムデザイン・マネジメントを学んだことを活かして、その裏側にある理論を分析している。実例に触れて「そんなの浮かばないわ」に留まるのではなく、どのような見方、考え方がヒントを引き寄せるのか、反対に、自分や組織の抱えている課題が何かを探っていく指針になる。
本当に多くの例が登場しているが、RIZAPが展開している「chocoZAP」について取り上げた章で述べられている「まずはやってみる」という考え方は、行動になかなか移せない自分が改めて取り入れなければならないことである。「コンビニジム」という、他のフィットネスジムにはない面が売りである。フィットネス以外に何が求められているかというのを模索し、社員たちの提案したものをまず置いてみる。残らなかったものの方が多いのだろうが、セルフネイルや脱毛ができるというのは「とにかく出してみる」という段階を踏んでいることによる。PDCAサイクルのC(check)を充実させるために利用者アンケートも積極的に行っており、そのためにPlanとDoをできる限りスピーディーに進めるというのが徹底されている。何となくではなく目的を持ってサイクルを回すことがやはりアイデアを生み出すきっかけにもなりえるのだ。
徳野のおすすめビジネス書
辻太一朗/曽和利光/細谷修平/矢矧春菜 『採用一新 さらば!ガクチカ頼み』 株式会社日経BP
講師の採用面接の時間が迫るといつも憂鬱な気分になる。他者の人格をテストするような行為じたいに(今でも)気が引けるし、30分近く色々と話し込んだ相手を場合によっては落とさないといけないからだ。加えて、そもそも「良い人材」を見極める基準や方法が自分の中で明確になっていないのも不安の種だ。他の社員による面接に同席した機会は何度かあるものの、それの「見よう見まね」のような状態でここまで来てしまった。一教室の責任者としてそれでは流石にまずいと感じて手に取ったのが今回の一冊である。
4人いる著者たちは皆、リクルート社の「学ポタ」推進委員会のメンバーである。この「学ポタ」、正式名称は「学業場面に表れるポータブルスキル」は、新卒の就活でよく取り沙汰される「ガクチカ」、つまり「学生生活で力を注いだこと」に対置される概念だ。日本の大学生は欧米や中国の若者と比べると入学後の勉強量が少なく、国際競争力で引けを取る一因になっているという言説を耳にするが、それは企業による採用のあり方が生んだ構造的な問題である。インターネット経由の応募が一般的になって以降、膨大な情報処理を求められるようになった企業は、エントリーシートと性格適性テストを用いて効率性を追求し始めた。その影響で、大学での専門研究よりも親近感の湧くサークル活動やボランティア、アルバイトでの経験が注目を受けやすくなった。また、就活生側も短い時間で採用担当者に強い印象を与えることを目指して「伝え方」を洗練させる方に重きを置くようになり、エピソードの脚色も横行し出した。すると、演出力のある応募者に有利な状況が作り出されることになるが、その現状は学生たちの内に「自分の事を正直に語っても選考に通らない」という先入観を植え付けているだけでなく、人材のミスマッチを防ぎたい採用担当者は相手が語る内容の真偽を見極めることに注力するようになった。互いに心理的負担が大きいのだ。
そして、「学ポタ」は就活に関わる不信感を軽減するために考案されたシステムである。採用の確実性を高めるための着目するべきポイントは「定量的な成果」と「思考の一貫性」であり、それを測る上で学業の成績は最適な素材となる。さらに、GPAなどの数値化された「結果」だけではなく履修科目の内容や単位の取得難易度も可視化することで、学生の知的好奇心の方向性や目標に対する計画性を浮き彫りにしやすくなる。それらは仕事の現場で生きる素質だ。さらに、企業側が信頼に足るデータを求めることは若者たちへの「メッセージ」にもなるので、学生たちの間に「まずは腰を据えて勉強するべきだ」という価値観を浸透させる効果も期待できる。
個人的な話に戻るが、本作を読み始めてから学生講師との面接が2件あった。緊張は相変わらず襲ってきたものの、受験に関して「なぜ、今通っている大学と学部に決めたのか」、第1志望校と縁が無かった場合は「自身の受験をどう振り返っているか」を教えてもらうことの狙いをきちんと把握した上で臨めたのは一つの収穫だ。あとは、19歳の若者たちの具体的な夢についてあれこれ掘り下げるのは純粋に楽しかった。