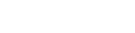弟が生まれる8歳まで私は一人っ子でした。志高塾に入塾したのは小学4年生の頃です。当時の私は誰もが認める問題児で、ある日唐突に家を飛び出して公園に泊まってみたり、こっそりお酒を飲んでみたり、志高塾で悪さを働いて家に帰らされたこともあります。後にも先にも、松蔭先生が家庭訪問を行ったのは楢﨑家だけだそうです。そんな問題だらけの私が、入塾から10年以上の時を経て、不思議なことに卒業生の一人として文章を書くことになりました。
幼い頃から大のいたずら好きで、人にちょっかいをかけることが多かった私は、まず集中して要約作文を書きあげることを目標に志高塾へ通うこととなりました。しばらくして、自分は集中するまでが難しいものの、一度そのモードに入ってしまえば最後までスラスラと書けてしまうことに気が付きました。その時、初めて勉強することが楽しいと感じて、気持ちが高揚したことを今でもよく覚えています。もっとも、書き終えたらすぐに先生に見せたがるので、ミスばかりの原稿用紙を提出して、ちゃんと見直しをしなさいと注意されるまでがルーティーンでしたが。5年生の頃ぐらいに中学受験に臨むことを決めました。それは、親が望んだものでした。大学附属の小学校に通っていたのですが、親から説明を受けた後に興味本位で受験勉強を開始しました。ところが、勉強をすること自体が嫌いになっていきました。なぜなら、小学校にいた周りの生徒たちのほとんどが内部進学で中学に上がるため、私が塾に通う時間が増えれば増えるほど、彼らとの距離が遠のいていく気がしたからです。事実、私は彼らの興味を惹きたい一心でいろいろな行動を起こしましたが、学校と両親に迷惑をかける形ですべて失敗に終わり、最終的に私はクラスの中で異分子として扱われるようになりました。しかし、中学受験そのものには、なぜか成功しました。考えられる理由としては、志高塾の先生が受験対策の読解問題だけではなく、私が好きだった作文を並行してくれたからだと推測できます。その時期の私に嫌いなことだけをやり続けるだけの忍耐力は無かったです。目標としていた中学校に通い始めても、勉強をやる気にはなれず、作文を書くことにも嫌悪感を覚えるようになっていきました。そして、親のやさしさに甘えた私は、日本の勉強熱心な教育方法に嫌気がさしたと言い訳をして、高校からは海外へ留学することを決めました。文字通り、海外逃亡の始まりです。
ニュージーランドの現地校へは、高校一年生から三年間通いました。その間、勉強は全くと言って良いほどしておらず、現地でのコミュニケーションツールだったスポーツと遊びにほとんどの時間を費やしました。どうすれば周りのニュージーランド人に認めてもらえるのか、そればかり考えていたのです。しかし、残念なことに、小学校の時と同様に失敗に終わりました。寮生活であったため三年間同じ屋根の下で過ごしましたが、彼らとは表面上の関係しか築けず、ついにはそこにあった境界線を越えることはできませんでした。英語のスピーキングとリスニング能力は向上したものの、読み書きに関しては微々たる成長しかできませんでした。
さて、そのような高校生活を送っているうちに、コロナ禍を経ていつの間にか卒業を迎え、二年半ぶりに日本へ帰国することとなりました。久しぶりの日本を堪能するつもりでしたが、実際に帰国すると、大学にも通わずに遊ぶことに対する違和感と罪悪感が日に日に自分の中で大きくなっていきました。三年間の留学はなんだったのか、これから自分はどの道を進めばいいのか、ただ焦りと不満が募っていく日々でした。そんなとき、お先真っ暗な私に光を照らしてくれたのが松蔭先生でした。松蔭先生とは留学中も何度か連絡は取っていたため、その状況を見かねて、日本で大学受験をすることを条件にもう一度志高塾で面倒をみてやると言ってくださいました。志高塾での二回目の受験勉強の始まりです。そこからの一年間、私は先生の下でたくさんの文章を書きました。最初は、自分がどのような人間であり、どんなことに興味があるのかを知るために、徹底的に自己分析を行いました。その過程で、意見作文を書き始めたのですが、自分がいかに無知であるかを思い知らされました。そして、それまで物事について調べたり考えたりをしてこなかった私は、その大きなビハインドを痛感すると同時に、無知であることに恥じらいをも感じました。どこから始めれば良いかも分からず右往左往している私に、先生は、本の読み方や情報の調べ方を、丁寧に何度も教えてくださいました。そうして先生と共にいろいろな情報をインプットすることで、次第に様々なことに興味を持ち始めることができました。すると、これまではモノトーン色にしか見えなかった世界が、実は色鮮やかで美しいものであることに気づかされました。これは比喩表現ですが、私は実際に世界が色めいていく瞬間を目の当たりにしました。松蔭先生は、志高塾での時間を通じて、私に勉強することの楽しさを思い出させてくれました。そんな幸せな一年はあっという間に過ぎてしまいました。作文のテーマとしても何度も扱っていた社会問題をより深く勉強したいと考えた私は、立命館アジア太平洋大学のサステイナビリティ観光学部に入学しました。現在は、ダブル・ディグリー制度を利用して、オーストリアのザルツブルクにある大学に2年間の留学中です。
私の世界が色めき始めたころ、教室で松蔭先生と次のような会話をしたことを覚えています。「小さい時のことは覚えてへんと思うけど、兄弟の間で親から一番愛情をもらってるのは、絶対に長男長女やで。」私もその通りだと共感しましたが、親子の距離感は、子供が成長するにつれて少なからず変化していくものです。特に、弟妹が生まれると、それまで自分に100%向けられていた愛情が他のところにも分散するので、とても虚しい気持ちになります。今思えば、私はその時からずっと寂しかったのかもしれません。遠のいていく親の気を惹きたくて反抗してみたり、あえて物理的に距離を取ったり、小学校ではクラスメイトに、ニュージーランドでは現地の人たちに、ただ構ってほしかっただけなのかもしれません。贅沢な悩みやな、と突っ込まれてしまっては返す言葉もありませんが、先生は、そんな不器用な私の感情に応えてくれました。丸一年かけて、教育という名の愛情をもって、私を導いてくださいました。そんな教育熱心で温かい愛情に救われたのは、きっと私だけではないはずです。志高塾は19年目に入り、先生はこれまで私を含む多くの生徒を支えて来られました。そして、これからもたくさんの小さな芽を育てていくことでしょう。
志高塾で培われた私の言葉が、文章が、経験が、種類は違えど私と同様一筋縄では行かないお子様と毎日奮闘している親御様のお役に少しでも立てたのであれば幸いです。