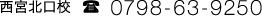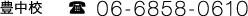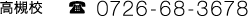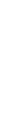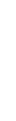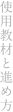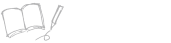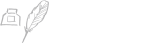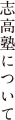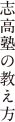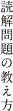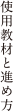2022.05.17Vol.543 「なぜ」の行きつく場所
今回はある講師の文章を紹介いたします。彼女は学生講師として2年、社員として2年働いたのち、昨年の4月からは非常勤として授業外の仕事をしています。現在、志高塾として意見作文用のものを中心に教材の充実を図るべく動いておりますが、その中心的な役割を担っているのが彼女です。以下は原文のままであり、「松蔭さん」という表現がありますが、それは内部向けに書かれたもの(初稿は4月初旬に私の手元に届きましたが、そこから彼女自身が修正を繰り返しました)だからです。また、タイトルの、「なぜ」の行きつく場所、も彼女の付けたものです。
来週は、GWに頑張った分の振替としてお休みですので、次回は5月31日になります。
「エンパシー」という言葉は、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(ブレイディみかこ、新潮社、2019年)を読んで知った。それを直接的に扱っているのは16章あるうちの1章のみだが、「誰かの靴を履く」という英語の定型表現とともに、ひときわ強く印象に残っている。
著者のブレイディさんはいくつかの辞書を参照しながら、「エンパシー」の語義を「自分と違う理念や信念を持つ人や、別にかわいそうだとは思えない立場の人々が何を考えているのだろうと想像する力」というように表現している。一方、似たような言葉である「シンパシー」は、「かわいそうな立場の人や問題を抱えた人、自分と似たような意見を持っている人々に対して人間が抱く感情」といった定義がなされている。日本語圏内で生活しているわたしでも、後者は「共感」や「同情」といった訳がなんとなく思い浮かぶくらいにはなじみがあるし、そうした感情なら普段いくらでも生まれているような気がした。だからこそ、上記の違いを知った当時、志高塾に通う子どもたちにはぜひ「エンパシー」に触れてほしい、単に用語として知るだけでなく、その能力を用いる時間を持ってほしいと考え、意見作文基礎の題材の一つとして据えた。いや、その時点では、そこまではっきりとした意図はなかった。「みんな、このテーマでおもしろい作文書いてくれるんじゃないかな!」という大変安易な思いつきでしかなかったはずだ。
ずいぶんと長い前置きになってしまった。なぜ今この時「エンパシー」に思いを巡らせているのかといえば、ロシアのウクライナ侵攻について勉強する中で、まさにこの力を使う必要に迫られたからだ。本題に入る前に、立場を明確にしておくが、わたしは現在プーチンが主導しているウクライナへの軍事侵攻、侵略行為には、絶対に反対だ。
この事態が起こったのは2月24日。すでに1か月以上も経っているのに、わたしは今までこの問題にきちんと向き合えていなかった。予備知識がまったくないことも手伝い、連日のニュースだけでは、どうしても無力感や絶望感など、即時的なリアクションばかりが先行してしまっていた。書店に並ぶ関連書籍にも、「これを読んだところで、わたしにはなんにもできないじゃないか」と、なかなか手が伸びなかった。募金をしても、ある種の罪悪感が募るだけだった。そんな中、しばらく聞いていなかった「COTEN RADIO(コテンラジオ)」というポッドキャストの番組、そのラインナップをなにげなく眺めていると、「特別編 ウクライナとロシアの歴史」というテーマで6回分の放送をしていたことが分かった(「歴史を面白く学ぶ」がコンセプトの当番組は、2年ほど前に松蔭さんから教えて頂いた)。緊急収録されたそれは、今回の出来事の「解像度」を上げることが目的とされており、ウクライナやロシアのルーツから、現在に至るまでの経緯や系譜を追っている。なお、その初回放送の冒頭において、これから話す内容は、あくまで日本に住む自分たちがアクセスしうる30冊ほどの書籍を読んで得た知見やファクトであり、この出来事に関して自分たち以上に精通している専門家は山ほどいる、という前提が冒頭で明確に示されていた。始まった瞬間「あ、これは聞いてるだけじゃだめだ」と気づいて、ノートと筆箱を引っ張り出し、とにかく一つでも多くの情報を書きとめようとした。それこそ学生時代に戻ったように、必死に。
一を聞いて十を知るどころか、十聞いても一知ることができたかどうか、今の自分にはそれすら難しい。ただ、長い歴史をさかのぼる中で、「なぜそうなったのか」が少しずつ浮き彫りになっていくのはひしひしと感じられた。自分にとって、これまで得体の知れなかったロシア連邦という世界最大の国が、そしてそれを率いるプーチンが過去にたどってきた道のりを少しでも知ることで、それらはある程度俯瞰できるまでに、立体的かつ多面的にたちのぼってきた。次の段落は、ラジオを聞き、その後他の文献やニュースを参考にして認識が更新された部分を、備忘録として自分なりにまとめた内容だ。特にこの部分については、いくら書き直しても、納得がいかない。どんな言葉にしても、何か違うような気がする。これじゃだめだと、うなだれる。書けば書くほど、自分がいかに何もわかっていないのかを思い知らされる。それでもなお、何かを書こうとするのは、何も知らないままで、わかったつもりのままでやり過ごしたくないからだ、と思う。
およそ1000年前の大国「キエフ・ルーシ公国」は、ウクライナの首都キーウを中心とした国家であり、これを形成した東スラヴ人が、現在のウクライナ人、ロシア人、ベラルーシ人の祖先となる。この国がモンゴルの征服によって終焉すると、「最初のウクライナ国家」と呼ばれるハーリチ・ヴォルイニ公国が誕生するものの、1世紀ほどで滅亡し、リトアニアとポーランドに併合されてしまう。その後300年もの間、ウクライナを代表する政治権力がその地には存在しなかったが、それにもかかわらず、ウクライナは、ロシアともベラルーシとも異なる独自の文化、言語を育んでいった。17世紀にはコサックと呼ばれる自治的な武装集団によってウクライナ・ナショナリズムの動きが生まれ、独立を求める不撓不屈の精神は、18世紀末からロシア・オーストリア両帝国によって支配される中でも、第一次世界大戦後に四か国の分割統治下に置かれても、ソ連に編入された時代においても、決して失われることはなく、1991年のソ連崩壊とともにやっとのことで独立を果たした。
一方のロシアは、上記の「キエフ・ルーシ公国」滅亡後にモスクワ公国として力を伸ばし、拡大していった。しかしその中で、モンゴルやナポレオン、ナチスなどの外敵脅威を何度も経験したこの国は、切り崩され崩壊していく恐怖心を常に抱えてきたハートランドである。同じユーラシア大陸でも、言語も文化も宗教も異なる「西側」には、近代化において後塵を拝し、民主主義対社会主義という構図の中でもソ連崩壊という形で敗北した。いずれも、いわゆる「国民国家」としてまとまりきれなかったことが一因であると考えられる。また、一つの国家へと束ねにくいのは、その土地があまりにも広大すぎるからであり、そこに多種多様な民族が入り乱れているからだ。たとえば、19世紀後半の鉄道建設や製鉄業を主とした工業化に際し、ウクライナへ多くのロシア人が流れ込んだ。独立したウクライナには20%のロシア人が残っていたという。どこまでがロシアで、どこから先がロシアではないのか。誰がロシア人で、誰がロシア人ではないのか。島国に住むわたしにはなかなかイメージがつかないほど、境界線を引きづらいあの大陸において、自らのアイデンティティ、ルーツ、自国意識を確立させるのは困難だ。
そんなロシアにとってウクライナはかつての「小ロシア」「旧ソ連国」であり、豊かな穀倉地帯と発達した工業都市、さらには黒海に面した「不凍港」を持つ。天然ガスを用いた重化学工業においてこの二か国が密接な関係にあることは言わずもがなであり、そのうえ、バルト三国も加盟したNATOとの距離をとるという意味では、緩衝地帯としての役割も大きい。つまり、ロシア(プーチン)の視点に立てば、欧米諸国の囲い込みによって疎外され、着実に「勢力圏」を削がれつつあるかつての大国を守り、もう一度「強いロシア」を復活させるというストーリー、そのためには、地政学的にも経済的にも枢要なウクライナをどうしても自らの「勢力圏」に置かねばならないという一貫したロジックが見えてくる。
もちろん、そんな理屈を武力行使で、しかも二度の世界大戦を経て深く反省してきたはずのこの時代に押し通そうとするのは、間違っている。『物語 ウクライナの歴史』(黒川祐次、中央公論新社、2002年)によれば、長い歴史の中で常に近隣諸国からの侵略を受け続けてきたウクライナは、「国がない」というハンディキャップを持ちながらも、そのアイデンティティを失わず、独自の言語、文化、習慣をつくりあげていったとある。何度支配されても、何度阻まれても、大きな犠牲を払いながら独立を目指し続けてきたのである。どんな理由があっても、戦争という形でその意志を踏みにじるのは、間違っている。
だが、今までのわたしは、この「間違っている」という感覚だけしかわからなかった。いや、今だって、本当は何にもわかっていない。きっと何にもわかっていないのだけれど、「なぜそうなったのか」を問うことで、ようやく、考え始めることができた。ようやく、思考のスタートラインに立てたように思う。扇動的なメディア、真偽の曖昧な情報に気持ちを揺さぶられながらも、それを抑えこみ、「なぜ」を問うこと。自分なりに考え続けること。「それしかできない」は、やり方ひとつで「それができる」に変わるかもしれない。反射的に「間違っている」と叫ぶことと、たくさんの「なぜ」を経て「それでも間違っている」と断言すること。結論は同じでも、その言葉の重みや深さには大きな隔たりがあるはずだ。
ここまで考えてきて思い至ったのは、やはり志高塾の作文だった。意見作文のみならず、初歩教材である『コボちゃん』や『ロダンのココロ』の要約でも、オチや全体の流れを捉えるために、「なぜそうなったのか」を考慮することが非常に重要になってくる。最後の一コマを切り取っだだけでは、その面白さは掴めない。コマ同士のつながりを意識しながら、「何が起こったのか」「それについてどう思うか」だけでなく、「どうしてそうなったんだろう」という問いを立て、自分なりに思考しなければならない。情報に深く切り込み、的確に理解するためには、そうした「なぜ」の姿勢が不可欠だ。そのような思考の力を身につけるために、志高塾に通う子どもたちは、うんうんうなりながら作文を書いている。そのような思考の力を身につけてもらうために、先生たちは粘り強く指導している。そんなこと、わかっていたつもりだった。でも、本当に「つもり」だった。今日までちっともわかっていなかったという事実を、今更ながらに痛感する。
ウクライナとロシアの件に関して、ラジオに耳を傾けながら「なぜ」を問わねばならなかった時、わたしは渦巻く感情を一旦抜きにして、ウクライナの歴史ではウクライナの視点から、ロシアの歴史ではロシア(プーチン)の視点から物事を考えざるをえなかった。とりわけ後者に関しては、歴史的にも地理的にも、プーチンの謎に満ちた生い立ちも、理屈も理想も、何もかもがわたしの見てきた世界とはまったく異なり、共感も賛同もできない。それでも、今の自分にできる範囲ではあるが、客観的に想像しようとすることはできた。「自分と違う理念や信念を持つ人や、別にかわいそうだとは思えない立場の人々が何を考えているのだろうと想像する力」。「エンパシー」は、「なぜ」が発せられた時に、ごく自然に発揮されているような気がする。もしそうであれば、志高塾に通う子どもたちはどの教材に取り組んでいる時でも、多かれ少なかれ「なぜ」と向き合い続けているはずで、それを考えるために、知らず「エンパシー」なる力を駆使していることだってあるかもしれない。そんなささやかな気付きを得るだけで、わたしが見ている世界は、ほんの少し明るく、ほんのりあたたかみを帯びていく。かれらに負けないよう、わたしも、日々「なぜ」を問い続けていきたい。
蛇足になるが、最後にもう一つだけ。「なぜ」という問いかけは、何かを不思議に思ったり、疑問を感じたりしたときに生まれる。だが、日々のニュースを目にした際に浮かぶ「なぜ」の底深くには、あらゆる理不尽、暴力、不寛容に対する憤りや悲しみが、ある。何度も何度も、たくさんの「なぜ」を自分に問い続けて、俯瞰して、あらゆる「事実」や「正解」や「間違い」を目の当たりにして、自分なりの結論を出した時、それでもそこに混じった一抹の感情は、物事をどんなに客観的に突き詰めても消え去らなかった感情の残滓は、きっとその人がその人たるゆえん、証明、「その人らしさ」なのだろう。論理的な思考の中に収まりきらない、地中から湧き出る泉のように清らかな思いも、あるいは泉の底に沈んでいる澱にも似た感情でさえも、大切に守られるべき「その人らしさ」なのだと思う。